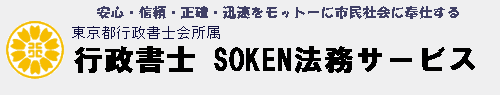建設業を営むためには、「経営業務管理責任者がいること」「専任の技術者がいること」「請負契約に関して誠実性のあること」「財産的基礎または金銭的信用があること」「一定の欠格要件に該当しないこと」の5つの要件を満たしているかどうかの審査を受け、始めて、建設業の許可を取得することができます。以下、各要件の概要についてご説明いたします。
【1】経営業務管理責任者がいること
経営業務管理者とは、法人の場合は、常勤の役員(株式会社、有限会社での取締役などで監査役は該当しません)であること、個人の場合には、事業主本人または支配人であることに該当しなければなりません。また、以下の1〜3の何れかの条件に該当する必要があります。
1.許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務管理責任者(法人役員、個人事業主)としての経験があること。
2.許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上の経営業務管理責任者としての経験があること。
3.許可を受けようとする建設業に関し、7年以上の経営業務管理責任者に準ずる地位にあって経営者を補佐(ここで いう「補佐」とは、法人での役員に次ぐ立場(建設部長など)や個人では、妻子、共同経営者など)した経験があること。
【2】専任の技術者がいること
専任の技術者とは、担当する業務について専門的な知識や経験をし、営業所でその業務に従事する(専属に)者です。
専任の技術者は、その営業所に常勤し、専門にその職務に従事する者でなければなりません。そのため、他社からの出向社員は、自社の専任技術者とすることは原則としては認められません。しかし、通達によると「勤務状況、給与の支払い状況、人事権の状況等の判断基準から専任性が認められる場合には、出向社員でも専任の技術者として取扱う」(平成6年9月30日経建発289号)となっていることからみて、その対応は、ケースバイケースともいえます。
また、「一般建設業」と「特定建設業」でも異なりますので以下を参照下さい。
■一般建設業の場合
許可を受けようとする業種が「一般建設業」の場合、以下の1〜3の何れかに該当する必要があります。
1.大学または高校で申請業種に関連する学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の申請業種についての実務経験(許可を受けようとする建設工事の技術上の経験をいう。具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験および実際に建設工事の施工に携わった経験のこと)がある者。
2.学歴を問わず、申請業種について10年以上の実務経験がある者。
3.申請業種に関して法定の資格免許を有する者(1・2級建築士、1・2級土木施工監理技士、電気工事士など)、その他、国土交通大臣が個別の申請に基づ認めた者。
■特定建設業の場合
許可を受けようとする業種が「一般建設業」の場合、以下の1〜3の何れかに該当する必要があります。
1.申請業種に関して法定の資格免許がある者(1級建築士、1級土木施工管理技士、1級電気工事施工管理技士な ど)
2.一般建設業許可の技術者の要件を満たし、かつ、許可を得ようとする建設業に係る建設工事で発注者から直接請 け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し、2年以上の指導監督的な実務経験(建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験をいう)がある者。
3.国土交通大臣が、上記1または2に掲げる者と同等以上の能力があると認定した者。
【3】請負契約に関して誠実性のあること
「誠実性のあること」とは、不正または不誠実な行為をするおそれがないことであり、「不正」「不誠実」な行為としては、以下のような行為があげられます。
◇不正な行為‥‥請負契約の締結または履行に際し、詐欺・脅迫・横領などの法律に違反する行為。
◇不誠実な行為‥‥工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為。
上記の行為は、法人の場合、法人自体または役員もしくは政令で定める者(支配人、支店長もしくは営業所長など支店または建設業上の代表者)であり、個人の場合には、個人事業主または政令で定める者が問われることとなります。
【4】財産的基礎または金銭的信用があること
「財産的基礎」とは、自己資本額などの財務基盤のことです。また、「金銭的信用」とは、資金調達能力のことです。許可の要件として、工事の適正な施工や発注者の保護などのため、一定の「財務的基礎」を求められます。ただし、一般建設業の場合には、財務的基礎がなくとも「金銭的信用」があれば、その代わりとなります。
■一般建設業の場合
以下の1〜3の何れかに該当することが必要です。
1.自己資本額が500万円以上であること。
尚、この場合の「自己資本」とは、貸借対照表の「資本の部」の「資本合計」の額をいいます。
2.500万円以上の資金を調達する能力があること
資金調達能力とは、金融機関から資金の融資を受ける能力があるかどうかです。その能力は、預金残高証明書、融資可能証明書、固定資産納税証明書、不動産登記簿謄本などで証明します。担保となる不動産があることは優位に働きます。
3.許可の更新の場合は、更新申請の直前5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること。
■特定建設業の場合
以下の1〜3の全てに該当することが必要です。
尚、許可申請者が財産的基礎を有しているかどうかについては、原則、申請直前の財務諸表で判断されます。
1.欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
2.流動比率が75%以上であること
3.資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
【5】一定の欠格要件に該当しないこと
以下の1〜10のいずれの欠格要件にも該当しないことが求められますので、くれぐれもご注意下さい。
1.成年被後見人もしくは被補佐人または被破産者で復権を得ないもの
2.不正の手段で許可を受けたこと、または営業停止処分に違反したこと等により、その許可を取り消されてから5年を経過しない者
3.許可の取り消しを免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しないもの。
4.上記3の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内にその法人の役員であった者で、その届出の日から5年を経過しないもの。
5.営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者。
6.営業を禁止し、その禁止の期間が経過しない者。
7.禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
8.建設業法または一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
9.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年で、その法定代理人が上記1〜8のいずれかに該当するもの。
10.許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実を記載を欠いたとき。
|